某公立学校ことばの教室教員。公認心理師、言語聴覚士、特別支援教育士。
『クイズで学ぶことばの教室基本の「キ」』の著者。
SINCE 2000.1.1
プロフィール
ハンドルネーム ya
某公立学校通級指導教室担当教員
言語聴覚士
特別支援教育士(S.E.N.S)
性別 男
■メールはこちら
■ツイッターはこちら
■ことばの教室ビギナーズ交流館(DVD頒布者限定パスワード)
■一日1クリックを。ランキングに反映します。
もくじ
ブログ内検索
カレンダー
最新コメント
[01/11 board]
[11/21 西村徹]
[02/23 留萌小学校ことばの教室]
[05/10 プー子]
[01/11 にくきゅう]
[11/25 なっか]
[10/26 さつき]
[10/12 赤根 修]
[08/21 赤根 修]
[05/28 miki]
[05/28 miki]
[05/13 赤根 修]
[05/06 赤根 修]
[04/15 miki]
[04/15 赤根 修]
[03/12 かわ]
[03/09 赤根 修]
[03/03 KY@札幌]
[03/01 赤根 修]
[02/28 hakarino]
[02/23 kさん]
[02/23 miki]
[02/12 suge]
[01/15 suge]
[01/15 miki]
アクセス解析
2025.12.16
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2012.09.07
発達を理解しないと、発達障害も理解できないですよ
構音指導の前に、十分遊んだ方がいいなあと思うことがあります。
からみあったり、くすぐりあったり。
発達が5歳ぐらいの子であれば、生活年齢ではなく、5歳に合わせた指導をすればいいわけです。
どうして生活年齢に合わせる必要があるのでしょうか?
社会に出たら縦割りの人間関係です。
同じ年齢の人が何十人も同じ部屋で仕事をする職場なんてあるのでしょうか?
同じ年齢同士で比較して、できる、できないなんていうのは、学校生活だけです。
その学校生活も、人生全体の長さに比べたら、ほんの一瞬です。
ならば、その子に今必要なことに合わせるのが一番いいのでは?
土台が積み上がっていない段階で、発音だとか読み書きだとか、バランスが悪いですね。
適時、適切、適量。
それは通常学級で支援員がつく、というだけではやりにくい、やはり個別指導の良さなのです。
個別だからこそ、十分に栄養を与えられることもあるのです。
集団との上手な使い分けによって。
個に合わせるためには、子どもの発達を見立てられなければなりません。
いわゆる標準的な発達というのがどういうものなのか。
それがわからなければ、発達障害もわかりません。
某初心者向けの研修会では、生育歴や発達の知識をたくさん教えられたという話を聞きました。
小手先の技術の前に、子どもを理解すること。
小手先の技術なんて、「コー○○○フォー」に行けば、いくらでも並んでいます。
特別支援教育コーナーや幼児教育あたりに行けば。
お口をいじる前に、先生の脚に抱きつく幸せを味わう段階ではないですか?
それさえも難しい家庭環境という場合もあるし、今がやっとその時期になった子だっています。
小手先の技術に走ると、そこから大きくずれていくのです。

応援の1日1クリックを!

↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
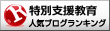
***
からみあったり、くすぐりあったり。
発達が5歳ぐらいの子であれば、生活年齢ではなく、5歳に合わせた指導をすればいいわけです。
どうして生活年齢に合わせる必要があるのでしょうか?
社会に出たら縦割りの人間関係です。
同じ年齢の人が何十人も同じ部屋で仕事をする職場なんてあるのでしょうか?
同じ年齢同士で比較して、できる、できないなんていうのは、学校生活だけです。
その学校生活も、人生全体の長さに比べたら、ほんの一瞬です。
ならば、その子に今必要なことに合わせるのが一番いいのでは?
土台が積み上がっていない段階で、発音だとか読み書きだとか、バランスが悪いですね。
適時、適切、適量。
それは通常学級で支援員がつく、というだけではやりにくい、やはり個別指導の良さなのです。
個別だからこそ、十分に栄養を与えられることもあるのです。
集団との上手な使い分けによって。
個に合わせるためには、子どもの発達を見立てられなければなりません。
いわゆる標準的な発達というのがどういうものなのか。
それがわからなければ、発達障害もわかりません。
某初心者向けの研修会では、生育歴や発達の知識をたくさん教えられたという話を聞きました。
小手先の技術の前に、子どもを理解すること。
小手先の技術なんて、「コー○○○フォー」に行けば、いくらでも並んでいます。
特別支援教育コーナーや幼児教育あたりに行けば。
お口をいじる前に、先生の脚に抱きつく幸せを味わう段階ではないですか?
それさえも難しい家庭環境という場合もあるし、今がやっとその時期になった子だっています。
小手先の技術に走ると、そこから大きくずれていくのです。
応援の1日1クリックを!
↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
***
PR

 管理画面
管理画面




