某公立学校ことばの教室教員。公認心理師、言語聴覚士、特別支援教育士。
『クイズで学ぶことばの教室基本の「キ」』の著者。
SINCE 2000.1.1
プロフィール
ハンドルネーム ya
某公立学校通級指導教室担当教員
言語聴覚士
特別支援教育士(S.E.N.S)
性別 男
■メールはこちら
■ツイッターはこちら
■ことばの教室ビギナーズ交流館(DVD頒布者限定パスワード)
■一日1クリックを。ランキングに反映します。
もくじ
ブログ内検索
カレンダー
最新コメント
[01/11 board]
[11/21 西村徹]
[02/23 留萌小学校ことばの教室]
[05/10 プー子]
[01/11 にくきゅう]
[11/25 なっか]
[10/26 さつき]
[10/12 赤根 修]
[08/21 赤根 修]
[05/28 miki]
[05/28 miki]
[05/13 赤根 修]
[05/06 赤根 修]
[04/15 miki]
[04/15 赤根 修]
[03/12 かわ]
[03/09 赤根 修]
[03/03 KY@札幌]
[03/01 赤根 修]
[02/28 hakarino]
[02/23 kさん]
[02/23 miki]
[02/12 suge]
[01/15 suge]
[01/15 miki]
アクセス解析
2025.11.05
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2010.11.23
【教材紹介】通級で使えるフリー学習ソフト 「漢チャレ君」
「漢チャレ君」
http://www.vector.co.jp/soft/win31/edu/se036053.html
シェアウェアです。
漢字の4択です。
学年別に出題され、登録者毎に成績が出ます。
Win3.1 仕様なので、古いパソコンでも。
とてもすぐれものです。
昔のソフトは、シンプルだけど、余計な装飾もないから、
すごく質が高いなあと思うのです。
***
ところで、漢字で思い出したのですが。
学習の遅れがあると、すぐにLDだとか、
逆に、LDは読み書き計算の問題だけなんだとか。
ちょっとステレオタイプかなあと。
まず、教育的なLDは、文字の読み書き計算の問題だけを指すのではないし、
知的な遅れに伴って、文字の読み書き計算も困難なら、LDではないわけです。
今の定義でいけば。
ただ、LDを知的障害があるかないかで分けることが無意味なのだと、
先進的な視点を持っているというならまだわかりますが。
ただ、たとえば「買う」という漢字の読み書きができないと言う前に、
その子は「買う」経験の束をどれだけもっているのか、という検証が大事かと。
1 お金を持って店に行く。
2 欲しい物をレジに持っていく。
3 レジが示した額のお金を渡すと、
おつりと商品が受け取れる。
その手続きをとれば、もう商品は自分のものだから、持って帰る。
4 その商品を消費する。
5 実はそのお金は、家族が汗水流して働いたからもらえたもの。
6 お金にも色々あって、足りないこともあれば、多すぎるときもある。
7 その他諸々
などの経験と、経緯の理解、言語概念の土台があって、
初めて「買う」ということばの意味、漢字の読み書きを指導する段階なのでは。
もっと言えば、たとえは「自分のもの」だって所有の概念。
誰の物か、ということは、人-物の単純な関係もあるけど、
みんなのもの、時と場合によって誰の物か変わる場合もある。
自分の物である場合と、人の物である場合とで、扱いがどう
変わるべきかというルール、暗黙知にも入ってくるわけです。
読み書き困難→LD→通級で学年を下げたプリントワーク→100点とった
ということだけで本当にいいのかなあ、と思うのです。
それも一つのやり方ではあるのでしょうけれども。
ちなみに、通級指導教室は、塾ではないですから、
教科の指導を中心にするというのは主旨にあっていないのです。
自立活動が中心とならなければならない。
学力向上というスローガンと、通級指導の主旨が混同している風潮も
最近感じているところです。
読み書きの指導ががその子の今にぴったりのこともあるでしょう。
それはそれでいいのですが。
しかし、その子の言語発達という縦軸の検討は必須だと思うのです。
たとえば、「読む」、「書く」の前に、「聞く」、「話す」はどうか。
最低限必要な観点です。
「買う」例で行けば、私なら「買い物ごっこ」をするかもしれません。
それは「買う」という漢字を覚えるために即効性はないかもしれないけど、
その子の長い人生を考えたとき、生きる力の土台として、
まず必要な指導は何か、と考えるのです。
その上で「買う」の読み書きをしたいのです。
***
記事タイトルからかなりかけ離れた、愚痴になってしまいました。
フリーソフト自体と、この愚痴とは何の関係もありません。
このフリーソフトも含めて、まず使う前に、子ども理解、ですね。


↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
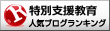
***
http://www.vector.co.jp/soft/win31/edu/se036053.html
シェアウェアです。
漢字の4択です。
学年別に出題され、登録者毎に成績が出ます。
Win3.1 仕様なので、古いパソコンでも。
とてもすぐれものです。
昔のソフトは、シンプルだけど、余計な装飾もないから、
すごく質が高いなあと思うのです。
***
ところで、漢字で思い出したのですが。
学習の遅れがあると、すぐにLDだとか、
逆に、LDは読み書き計算の問題だけなんだとか。
ちょっとステレオタイプかなあと。
まず、教育的なLDは、文字の読み書き計算の問題だけを指すのではないし、
知的な遅れに伴って、文字の読み書き計算も困難なら、LDではないわけです。
今の定義でいけば。
ただ、LDを知的障害があるかないかで分けることが無意味なのだと、
先進的な視点を持っているというならまだわかりますが。
ただ、たとえば「買う」という漢字の読み書きができないと言う前に、
その子は「買う」経験の束をどれだけもっているのか、という検証が大事かと。
1 お金を持って店に行く。
2 欲しい物をレジに持っていく。
3 レジが示した額のお金を渡すと、
おつりと商品が受け取れる。
その手続きをとれば、もう商品は自分のものだから、持って帰る。
4 その商品を消費する。
5 実はそのお金は、家族が汗水流して働いたからもらえたもの。
6 お金にも色々あって、足りないこともあれば、多すぎるときもある。
7 その他諸々
などの経験と、経緯の理解、言語概念の土台があって、
初めて「買う」ということばの意味、漢字の読み書きを指導する段階なのでは。
もっと言えば、たとえは「自分のもの」だって所有の概念。
誰の物か、ということは、人-物の単純な関係もあるけど、
みんなのもの、時と場合によって誰の物か変わる場合もある。
自分の物である場合と、人の物である場合とで、扱いがどう
変わるべきかというルール、暗黙知にも入ってくるわけです。
読み書き困難→LD→通級で学年を下げたプリントワーク→100点とった
ということだけで本当にいいのかなあ、と思うのです。
それも一つのやり方ではあるのでしょうけれども。
ちなみに、通級指導教室は、塾ではないですから、
教科の指導を中心にするというのは主旨にあっていないのです。
自立活動が中心とならなければならない。
学力向上というスローガンと、通級指導の主旨が混同している風潮も
最近感じているところです。
読み書きの指導ががその子の今にぴったりのこともあるでしょう。
それはそれでいいのですが。
しかし、その子の言語発達という縦軸の検討は必須だと思うのです。
たとえば、「読む」、「書く」の前に、「聞く」、「話す」はどうか。
最低限必要な観点です。
「買う」例で行けば、私なら「買い物ごっこ」をするかもしれません。
それは「買う」という漢字を覚えるために即効性はないかもしれないけど、
その子の長い人生を考えたとき、生きる力の土台として、
まず必要な指導は何か、と考えるのです。
その上で「買う」の読み書きをしたいのです。
***
記事タイトルからかなりかけ離れた、愚痴になってしまいました。
フリーソフト自体と、この愚痴とは何の関係もありません。
このフリーソフトも含めて、まず使う前に、子ども理解、ですね。
↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
***
PR

 管理画面
管理画面




