某公立学校ことばの教室教員。公認心理師、言語聴覚士、特別支援教育士。
『クイズで学ぶことばの教室基本の「キ」』の著者。
SINCE 2000.1.1
プロフィール
ハンドルネーム ya
某公立学校通級指導教室担当教員
言語聴覚士
特別支援教育士(S.E.N.S)
性別 男
■メールはこちら
■ツイッターはこちら
■ことばの教室ビギナーズ交流館(DVD頒布者限定パスワード)
■一日1クリックを。ランキングに反映します。
もくじ
ブログ内検索
カレンダー
最新コメント
[01/11 board]
[11/21 西村徹]
[02/23 留萌小学校ことばの教室]
[05/10 プー子]
[01/11 にくきゅう]
[11/25 なっか]
[10/26 さつき]
[10/12 赤根 修]
[08/21 赤根 修]
[05/28 miki]
[05/28 miki]
[05/13 赤根 修]
[05/06 赤根 修]
[04/15 miki]
[04/15 赤根 修]
[03/12 かわ]
[03/09 赤根 修]
[03/03 KY@札幌]
[03/01 赤根 修]
[02/28 hakarino]
[02/23 kさん]
[02/23 miki]
[02/12 suge]
[01/15 suge]
[01/15 miki]
アクセス解析
2025.11.06
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2010.11.15
日本の通級制度の幅をもっと広くしたい
国が定める通級対象である
「通常の学級での学習におおむね参加でき、
一部特別な指導を必要とする程度の者」
という範囲を超えて、通級対象としている事例があります。
また自立活動が主であり、教科の補充指導はあくまでも「従」なのが、
通級制度の趣旨ですが、
教科の指導が主になっているケースもあります。
検査や情報収集などをしないで、LDと判断してしまっているケースもあります。
これらは、通級制度の趣旨から見て妥当かどうか疑問があります。
ただ、考えて見れば、支援の必要な子で通級が良いと判断されるケースは、
国が設定している現在の通知・通達よりも、もっと多いはずです。
それを狭めているのは、第一に、人材の不足があります。
一方、特別支援学級に在籍する児童は、
特別支援学級での指導が「中心」となるようにカリキュラムを編成すること、
という縛りが、こちらの自治体ではでてきました。
「共同、交流学習」の主旨はどこへ行ってしまったのでしょうか?
通常学級に在籍し、通級の幅を広げていく方向と、
特別支援学級に在籍し、通常学級との交流、共同学習を広げていく方向とが
重なり合うように進めることが、これから大事なのでは、と思っています。
通常学級、通級、特別支援学級のそれぞれに連続性を持たせることです。
ならば、もっと柔軟に運用できるように、制度や人員を考える必要があります。
就学指導委員会で、保護者や本人が通級を希望し、
「通級妥当」と判断して、進学先の学校に答申したにもかかわらず、
教室が開設されなかった、という話は、少ない例ではありません。
通級が支援の全てではありませんが、小学校の通級で自信ややる気が育ったので、
進学先も継続してやって欲しい、というニーズがあることも事実です。
北海道では、中学校の通級指導教室担当教員は、10名の配置だそうです。
小学校の数百名とは大違いです。
関係者間の調整をどのようにしていけばよいか、頭の痛いところです。


↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
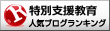
***
「通常の学級での学習におおむね参加でき、
一部特別な指導を必要とする程度の者」
という範囲を超えて、通級対象としている事例があります。
また自立活動が主であり、教科の補充指導はあくまでも「従」なのが、
通級制度の趣旨ですが、
教科の指導が主になっているケースもあります。
検査や情報収集などをしないで、LDと判断してしまっているケースもあります。
これらは、通級制度の趣旨から見て妥当かどうか疑問があります。
ただ、考えて見れば、支援の必要な子で通級が良いと判断されるケースは、
国が設定している現在の通知・通達よりも、もっと多いはずです。
それを狭めているのは、第一に、人材の不足があります。
一方、特別支援学級に在籍する児童は、
特別支援学級での指導が「中心」となるようにカリキュラムを編成すること、
という縛りが、こちらの自治体ではでてきました。
「共同、交流学習」の主旨はどこへ行ってしまったのでしょうか?
通常学級に在籍し、通級の幅を広げていく方向と、
特別支援学級に在籍し、通常学級との交流、共同学習を広げていく方向とが
重なり合うように進めることが、これから大事なのでは、と思っています。
通常学級、通級、特別支援学級のそれぞれに連続性を持たせることです。
ならば、もっと柔軟に運用できるように、制度や人員を考える必要があります。
就学指導委員会で、保護者や本人が通級を希望し、
「通級妥当」と判断して、進学先の学校に答申したにもかかわらず、
教室が開設されなかった、という話は、少ない例ではありません。
通級が支援の全てではありませんが、小学校の通級で自信ややる気が育ったので、
進学先も継続してやって欲しい、というニーズがあることも事実です。
北海道では、中学校の通級指導教室担当教員は、10名の配置だそうです。
小学校の数百名とは大違いです。
関係者間の調整をどのようにしていけばよいか、頭の痛いところです。
↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
***
PR

 管理画面
管理画面




