某公立学校ことばの教室教員。公認心理師、言語聴覚士、特別支援教育士。
『クイズで学ぶことばの教室基本の「キ」』の著者。
SINCE 2000.1.1
プロフィール
ハンドルネーム ya
某公立学校通級指導教室担当教員
言語聴覚士
特別支援教育士(S.E.N.S)
性別 男
■メールはこちら
■ツイッターはこちら
■ことばの教室ビギナーズ交流館(DVD頒布者限定パスワード)
■一日1クリックを。ランキングに反映します。
もくじ
ブログ内検索
カレンダー
最新コメント
[01/11 board]
[11/21 西村徹]
[02/23 留萌小学校ことばの教室]
[05/10 プー子]
[01/11 にくきゅう]
[11/25 なっか]
[10/26 さつき]
[10/12 赤根 修]
[08/21 赤根 修]
[05/28 miki]
[05/28 miki]
[05/13 赤根 修]
[05/06 赤根 修]
[04/15 miki]
[04/15 赤根 修]
[03/12 かわ]
[03/09 赤根 修]
[03/03 KY@札幌]
[03/01 赤根 修]
[02/28 hakarino]
[02/23 kさん]
[02/23 miki]
[02/12 suge]
[01/15 suge]
[01/15 miki]
アクセス解析
2025.10.28
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2013.01.20
WISC-IVの臨床的利用と解釈 3 ADHD、LDと下位検査、IQ
WISC-3においては、ADHDの判断のために、「注意記憶」だけをそのまま採用してはならない、ということは常識です。
たとえば、ADHDだから、「注意記憶」が有意に低いとは言えないということ。
これは私の経験上からも言えます。
ADHDにも、不注意優勢型、多動型、混合型とありますし、全部同じではない。
WISC-4では「注意記憶」が「ワーキングメモリ」になり、聴覚的なワーキングメモリを直接測る下位検査が出てきて、多くの因子が関わる「算数」が補助検査となりました。
ADHDとワーキングメモリとの関係については、報告もあるようですが、まだまだ研究途上なのでしょう。
文献を読んでいて、仮説を支持するものとしないものとがあって、頭がごちゃごちゃです。
文献では、数値とLD,ADHDとの相関についての論述ばかりで、子どもそれぞれの行動観察についての統計的な比較というものが見あたりません。(そんな統計は膨大すぎてできないでしょうが、多動な子どもを何とか席に座らせてやりましたとか、側に座ってやらせました、休憩を適宜入れながらやりました、という情報は見えないわけです。でも数値だけなら、その数値を出すまでの格闘が見えてこない)
そして、そもそも、ADHD、LDは、操作的な定義に過ぎないわけで、そのことと、発達検査との関係を考えるというのは結構大変なことだなあと。
学校の先生にできることは、検査時の行動観察や、答え方、そして、日常の行動観察、生育歴から判断する、というもっとも当たり前のことを地道にやること。
診断名でなく、その子によっての違いを見ていく、というところでしかないのでしょう。
そして、検査を行う人は、その検査の内容や認知モデルについて、かなり勉強しなければならないなと思いました。
だから、「ちょっと検査してみたら」という俗世間のとらえ方との間に、ものすごい開きを感じてしまいます。
血液検査とか、レントゲンとかと同じノリでとらえてしまうのですね。
検査を行う前に、情報収集によって、おおよその見立てと方向性ができあがっているということが大事でしょう。
検査はそれを裏付けるぐらいの姿勢で。
数値だけを伝えるというのは、やってはいけない、ということが、文献を読んでいてさらにわかってきました。
通級指導教室での様子だけでなく、関係者からの情報収集で見えてくるものがかなりあります。


↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
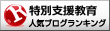
***
たとえば、ADHDだから、「注意記憶」が有意に低いとは言えないということ。
これは私の経験上からも言えます。
ADHDにも、不注意優勢型、多動型、混合型とありますし、全部同じではない。
WISC-4では「注意記憶」が「ワーキングメモリ」になり、聴覚的なワーキングメモリを直接測る下位検査が出てきて、多くの因子が関わる「算数」が補助検査となりました。
ADHDとワーキングメモリとの関係については、報告もあるようですが、まだまだ研究途上なのでしょう。
文献を読んでいて、仮説を支持するものとしないものとがあって、頭がごちゃごちゃです。
文献では、数値とLD,ADHDとの相関についての論述ばかりで、子どもそれぞれの行動観察についての統計的な比較というものが見あたりません。(そんな統計は膨大すぎてできないでしょうが、多動な子どもを何とか席に座らせてやりましたとか、側に座ってやらせました、休憩を適宜入れながらやりました、という情報は見えないわけです。でも数値だけなら、その数値を出すまでの格闘が見えてこない)
そして、そもそも、ADHD、LDは、操作的な定義に過ぎないわけで、そのことと、発達検査との関係を考えるというのは結構大変なことだなあと。
学校の先生にできることは、検査時の行動観察や、答え方、そして、日常の行動観察、生育歴から判断する、というもっとも当たり前のことを地道にやること。
診断名でなく、その子によっての違いを見ていく、というところでしかないのでしょう。
そして、検査を行う人は、その検査の内容や認知モデルについて、かなり勉強しなければならないなと思いました。
だから、「ちょっと検査してみたら」という俗世間のとらえ方との間に、ものすごい開きを感じてしまいます。
血液検査とか、レントゲンとかと同じノリでとらえてしまうのですね。
検査を行う前に、情報収集によって、おおよその見立てと方向性ができあがっているということが大事でしょう。
検査はそれを裏付けるぐらいの姿勢で。
数値だけを伝えるというのは、やってはいけない、ということが、文献を読んでいてさらにわかってきました。
通級指導教室での様子だけでなく、関係者からの情報収集で見えてくるものがかなりあります。
↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
***
PR

 管理画面
管理画面




