某公立学校ことばの教室教員。公認心理師、言語聴覚士、特別支援教育士。
『クイズで学ぶことばの教室基本の「キ」』の著者。
SINCE 2000.1.1
プロフィール
ハンドルネーム ya
某公立学校通級指導教室担当教員
言語聴覚士
特別支援教育士(S.E.N.S)
性別 男
■メールはこちら
■ツイッターはこちら
■ことばの教室ビギナーズ交流館(DVD頒布者限定パスワード)
■一日1クリックを。ランキングに反映します。
もくじ
ブログ内検索
カレンダー
最新コメント
[01/11 board]
[11/21 西村徹]
[02/23 留萌小学校ことばの教室]
[05/10 プー子]
[01/11 にくきゅう]
[11/25 なっか]
[10/26 さつき]
[10/12 赤根 修]
[08/21 赤根 修]
[05/28 miki]
[05/28 miki]
[05/13 赤根 修]
[05/06 赤根 修]
[04/15 miki]
[04/15 赤根 修]
[03/12 かわ]
[03/09 赤根 修]
[03/03 KY@札幌]
[03/01 赤根 修]
[02/28 hakarino]
[02/23 kさん]
[02/23 miki]
[02/12 suge]
[01/15 suge]
[01/15 miki]
アクセス解析
2025.02.02
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2016.04.03
知能検査の結果を保護者へ説明する際、適切なのはどれか。
2016.03.31
初めてことばの教室を担当する先生へ
初めてことばの教室を担当した先生は、何をどうやっていいのか、とまどっておられるのではないでしょうか。
「通級説明会で何を話したらいいかわからない」
「文書をどう処理すればよいかわからない」
そして
「指導の仕方がわからない・・・」
まずは慌てずに、しばらくの期間は子どもと楽しく遊び、信頼関係を作ることを重視してはどうでしょう。
「治そう」と思うと、子どもに加重な負担をかけたりするものです。
「この先生となら話したい」
「こいつとなら遊んでもいいや」
と子どもに思われるぐらいがちょうど良いのです。
肩の力を抜き、一人の人間として出会ってみては。
遊びながらも、一方では、子どもがどんな条件でどんな反応を示すか。その子の好きな遊びは。発音の専門的な検査の前に、一人の人間として聞いてみてどうかなど、まず指導方法よりも、子ども理解を。
指導が終わった後は、何でも気づいたことを「指導記録」に。どんなに拙い記録でも、数ヶ月後、数年後に役立つことも。
最良の「指導書」とは、どこか遠くにあるだけではなく、その子自身が「指導書」であること。
子どもをよく観察し、学級担任、保護者からも情報を頂き、何が問題なのかを考えてみてください。
「問題」とは「原因」ではなく、何に困っているかの事です。「困った子」ではなく「困っている子」。
そして「空き時間」には、文献にあたってみてください。
初めにハウツーものだけでなく、障害やその子についての深い理解が、その子に合った指導につながります。
わからないことがあったら、他のことばの教室の先生に遠慮なくきいてください。
どの先生にも「1年目」があり、悩み、迷いながら担当してきた経験があるのです。
そして理論も大事ですが、経験の長い先生の指導を見てください。
地域に研究団体があれば、経験の長い先生を紹介してもらってください。
近い方は、私の指導をごらんいただいても良いですよ。

↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
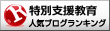
***
「通級説明会で何を話したらいいかわからない」
「文書をどう処理すればよいかわからない」
そして
「指導の仕方がわからない・・・」
まずは慌てずに、しばらくの期間は子どもと楽しく遊び、信頼関係を作ることを重視してはどうでしょう。
「治そう」と思うと、子どもに加重な負担をかけたりするものです。
「この先生となら話したい」
「こいつとなら遊んでもいいや」
と子どもに思われるぐらいがちょうど良いのです。
肩の力を抜き、一人の人間として出会ってみては。
遊びながらも、一方では、子どもがどんな条件でどんな反応を示すか。その子の好きな遊びは。発音の専門的な検査の前に、一人の人間として聞いてみてどうかなど、まず指導方法よりも、子ども理解を。
指導が終わった後は、何でも気づいたことを「指導記録」に。どんなに拙い記録でも、数ヶ月後、数年後に役立つことも。
最良の「指導書」とは、どこか遠くにあるだけではなく、その子自身が「指導書」であること。
子どもをよく観察し、学級担任、保護者からも情報を頂き、何が問題なのかを考えてみてください。
「問題」とは「原因」ではなく、何に困っているかの事です。「困った子」ではなく「困っている子」。
そして「空き時間」には、文献にあたってみてください。
初めにハウツーものだけでなく、障害やその子についての深い理解が、その子に合った指導につながります。
わからないことがあったら、他のことばの教室の先生に遠慮なくきいてください。
どの先生にも「1年目」があり、悩み、迷いながら担当してきた経験があるのです。
そして理論も大事ですが、経験の長い先生の指導を見てください。
地域に研究団体があれば、経験の長い先生を紹介してもらってください。
近い方は、私の指導をごらんいただいても良いですよ。
↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
***
2016.03.26
新設の通級指導教室
こちらの地方では、把握している範囲で、一教室が新規開設になるようです。
1 通級担当経験者が配置になる見通しであること
2 申請した複数の学校の中で、希望人数が一番多かったわけではない
2については、地域の実情や、要望の経緯等を踏まえた判断だったのでしょう。
また経験者が配置される見通しとなったことは、親の会との話し合いがある程度成果があったとも言えます。
このことは、他の教室の人事の状況も見ると、まず間違いない結論です。
また、運営にあたっては、
1 教科の勉強のためでなく、自立活動が主たる目的であること
2 指導時間割は通級担当が作成し、学級担任と都度調整すること
なかなか良い動きをしています。
他校の既設の教室からの助言が入っているのではないでしょうか。
心配したことがちゃんとクリアされていて、これまでの関係者の裏方での努力が成果として出ているのを感じます。

↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
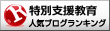
***
1 通級担当経験者が配置になる見通しであること
2 申請した複数の学校の中で、希望人数が一番多かったわけではない
2については、地域の実情や、要望の経緯等を踏まえた判断だったのでしょう。
また経験者が配置される見通しとなったことは、親の会との話し合いがある程度成果があったとも言えます。
このことは、他の教室の人事の状況も見ると、まず間違いない結論です。
また、運営にあたっては、
1 教科の勉強のためでなく、自立活動が主たる目的であること
2 指導時間割は通級担当が作成し、学級担任と都度調整すること
なかなか良い動きをしています。
他校の既設の教室からの助言が入っているのではないでしょうか。
心配したことがちゃんとクリアされていて、これまでの関係者の裏方での努力が成果として出ているのを感じます。
↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
***
2016.03.21
知的な遅れはなく、注意力も問題ないが、書く作業がとても遅い
2016.03.12
検査法で、もっとも適切な組み合わせはどれか。
2016.03.12
私自身の生育歴 どうして自分だけが違うんだろう
出生時体重 2500g。
くびのすわり 12ヶ月。
初歩 1歳6ヶ月。
1語文 2歳6ヶ月。
もう1人の「妹」は1500g。出生後数時間でこの世を去る。
母は食べ物が出産まで受け入れられず。
出産後も「怖くて」だっこもできず。
医師は出産まで、双子だとわからないぐらい、小さい2人だった。
幼稚園では泣いてばかりだった。
花火、突然の物音、鼻血でも泣いた。
幼稚園の盆踊りも怖かった。
人が楽しそうに語り合っているのが怖かった。
ゴミ一つが気になる。並んでいないと気になる。
人形の目が、テレビのアナウンサーが
自分だけを見つめているので怖い。
どうして自分だけが違うんだろう。
どうしてみんなは、家族と楽しそうにしゃべっているのだろう。
みんな、僕が習っていないところへ行って、
会話の勉強をしているに違いない・・・。

↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
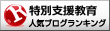
***
くびのすわり 12ヶ月。
初歩 1歳6ヶ月。
1語文 2歳6ヶ月。
もう1人の「妹」は1500g。出生後数時間でこの世を去る。
母は食べ物が出産まで受け入れられず。
出産後も「怖くて」だっこもできず。
医師は出産まで、双子だとわからないぐらい、小さい2人だった。
幼稚園では泣いてばかりだった。
花火、突然の物音、鼻血でも泣いた。
幼稚園の盆踊りも怖かった。
人が楽しそうに語り合っているのが怖かった。
ゴミ一つが気になる。並んでいないと気になる。
人形の目が、テレビのアナウンサーが
自分だけを見つめているので怖い。
どうして自分だけが違うんだろう。
どうしてみんなは、家族と楽しそうにしゃべっているのだろう。
みんな、僕が習っていないところへ行って、
会話の勉強をしているに違いない・・・。
↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
***
2016.03.06
小1女児。「自閉スペクトラム症」の診断あり。
2016.03.05
小2男児。言語発達遅滞。短期目標の設定で不適切なのはどれか。
2016.03.01
小1男児。科学的な仮説はどれか。
2016.02.28
検査の実施について、適切なのはどれか。
2016.02.27
不適切な通級指導
2016.02.21
「漢字の書きは上手だが、読めない」 エピソード理解の長所を生かした指導
Q 小3男児。漢字の書きは上手だが、書き順は一貫して誤る。読みは1年生レベルでもおぼつかない。ひらがなの読みはたどたどしいが、一度読めると単語を特定できる。国語の成績は学級で最下位。自由会話では、経験したことの言語表現は巧みだが、固有名詞を覚えるのが苦手な様子。生育歴にめだった問題はない。WISC-Ⅳではワーキングメモリが著しく低下し、他の合成得点は平均域で、信頼できる値。CARD(包括的領域別読み能力検査)では、音韻経路や、下位プロセスの弱さが目立つ。優先順位の低い指導はどれか。
1)漢字の書き順の指導
2)音韻分析課題
3)既有知識と結びついた漢字を精選して読み指導
4)漢字の成り立ちをイラストで指導
5)漢字を使って短文作成
***
上記の子の場合、たとえば、「消火」(ショウカ)と音読みで読むのは苦手で、「消す」「火(ひ)」と訓読みで覚えることは得意ではないか、と仮説が立てられます。
将来、
「けす、 ひ だから、ショウカだな」
と推理して読むこともできるようになるはずです。
エピソード理解、表現は得意なので。
せっかく検査を行っても、それが個別の指導計画なり、教材選択に生かされないなら、検査した意味がないだろう、と思っています。

↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
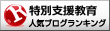
***
1)漢字の書き順の指導
2)音韻分析課題
3)既有知識と結びついた漢字を精選して読み指導
4)漢字の成り立ちをイラストで指導
5)漢字を使って短文作成
***
上記の子の場合、たとえば、「消火」(ショウカ)と音読みで読むのは苦手で、「消す」「火(ひ)」と訓読みで覚えることは得意ではないか、と仮説が立てられます。
将来、
「けす、 ひ だから、ショウカだな」
と推理して読むこともできるようになるはずです。
エピソード理解、表現は得意なので。
せっかく検査を行っても、それが個別の指導計画なり、教材選択に生かされないなら、検査した意味がないだろう、と思っています。
↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
***
2016.02.20
小1女児。サ行→タ行に一貫して置換
2016.02.14
教育的判断「学習障害」
2016.02.11
視覚、視機能、視知覚
2016.02.07
漸次接近法
2016.02.07
サ行がタ行に単音節で一貫して置換する小2男児
2016.01.30
検査結果の解釈について、正しいのはどれか。
2016.01.16
道の臨床研と、地元の言語研究会&就学指導委員会共催研修会 WISC 相談
1月14日の道言協臨床研究会にお呼ばれしました。
2つの事例レポートの検討と、構音基礎講座。
発表者お二人とも、子どものことを熱心に考えて、試行錯誤されていることに感銘を受けました。
子ども理解と指導の過程は、決して間違っていなくて、先生と子どもとの良い関係がこれからも伸びていくだろうと思いました。
一事例について、関わったことがある先生が様々な立場で参加できたことも大変有意義。
「スペシャリストとジェネラリスト」の両方の視点。
そして、問題行動に対して「折り合いをつける」。
この視点でお話させていただきました。
S.E.N.S-SVの先生からは、臨床クラスターによるWISCの解釈、再認と再生という視点を提供いただきました。ストンと胸に落ちました。きれいに解釈できるものですね。
そして、
「事例研は、どのような質問をするかがとても大事です。質問を考えることで、自分の担当する子どものことで悩んだとき、自分で自分に質問ができるようになる。そのことで子ども理解が深まるのです」
との大先輩のお言葉は、とても重厚でした。
そして、レポートの内容を大先輩が観点ごとに整理したプレゼンが秀逸でした。
収集した情報を整理するだけで、こんなにも子どもの状態像がクリアになるのかと。
「情報の整理」は子ども理解の重要な一過程です。
後半は、構音基礎講座。
言難ABCの内容をそのままやるよりも、事例を元に子ども理解と指導の手立てを考える、検査実技も盛り込む、ということの方が勉強になると考えました。
結果、ちょっと盛りだくさんで消化不良のところがあったかもしれません。
でも、構音だけでなく、子ども全体の理解の上で、指導の優先順位を考えるということの大切さは共有できたかと。
感想シートを後日拝見し、今後の参考にしようと思います。
15日は地元の就学指導委員会と、言語研究団体との共催研修会。
相談申込み受理から、事前の情報収集、必要な検査や観点の準備。
そして各種検査の概観と、検査実技、知能モデルの概要、面接演習まで、
講座全体で、一事例の相談というストーリー仕立てにしました。
就学指導委員とことばの先生の相談の力量アップが目的でしたが、自分の学校の通常学級担任、支援員、近隣の特別支援学校の先生など、様々な方が参加しました。
お昼のバイキングでは、先生同士の交流もできたようです。
お昼の交流も重要な研修と考えています。
これまで、就学指導委員向けの研修は、公的には企画も立案も運用もできないできたようです。
だから民間活力を使ったわけです。
公と民がコラボして、足りないところを補い合い、連携していくこと。
団体の組織力が弱まっている中、これからますます重要な取り組みと感じます。

↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
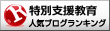
***
2つの事例レポートの検討と、構音基礎講座。
発表者お二人とも、子どものことを熱心に考えて、試行錯誤されていることに感銘を受けました。
子ども理解と指導の過程は、決して間違っていなくて、先生と子どもとの良い関係がこれからも伸びていくだろうと思いました。
一事例について、関わったことがある先生が様々な立場で参加できたことも大変有意義。
「スペシャリストとジェネラリスト」の両方の視点。
そして、問題行動に対して「折り合いをつける」。
この視点でお話させていただきました。
S.E.N.S-SVの先生からは、臨床クラスターによるWISCの解釈、再認と再生という視点を提供いただきました。ストンと胸に落ちました。きれいに解釈できるものですね。
そして、
「事例研は、どのような質問をするかがとても大事です。質問を考えることで、自分の担当する子どものことで悩んだとき、自分で自分に質問ができるようになる。そのことで子ども理解が深まるのです」
との大先輩のお言葉は、とても重厚でした。
そして、レポートの内容を大先輩が観点ごとに整理したプレゼンが秀逸でした。
収集した情報を整理するだけで、こんなにも子どもの状態像がクリアになるのかと。
「情報の整理」は子ども理解の重要な一過程です。
後半は、構音基礎講座。
言難ABCの内容をそのままやるよりも、事例を元に子ども理解と指導の手立てを考える、検査実技も盛り込む、ということの方が勉強になると考えました。
結果、ちょっと盛りだくさんで消化不良のところがあったかもしれません。
でも、構音だけでなく、子ども全体の理解の上で、指導の優先順位を考えるということの大切さは共有できたかと。
感想シートを後日拝見し、今後の参考にしようと思います。
15日は地元の就学指導委員会と、言語研究団体との共催研修会。
相談申込み受理から、事前の情報収集、必要な検査や観点の準備。
そして各種検査の概観と、検査実技、知能モデルの概要、面接演習まで、
講座全体で、一事例の相談というストーリー仕立てにしました。
就学指導委員とことばの先生の相談の力量アップが目的でしたが、自分の学校の通常学級担任、支援員、近隣の特別支援学校の先生など、様々な方が参加しました。
お昼のバイキングでは、先生同士の交流もできたようです。
お昼の交流も重要な研修と考えています。
これまで、就学指導委員向けの研修は、公的には企画も立案も運用もできないできたようです。
だから民間活力を使ったわけです。
公と民がコラボして、足りないところを補い合い、連携していくこと。
団体の組織力が弱まっている中、これからますます重要な取り組みと感じます。
↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
***
2016.01.16
通常学級の小中学生の通級で、法的に正しいのはどれか。
通常学級の小中学生の通級で、法的に正しいのはどれか。
① 校内の特別支援学級への通級は、認められない。
② 近隣の療育センターへの通級は、施設の位置づけが不明確なら認められない。
③ 軽度難聴の子が、授業時間に近隣の聾学校へ通級するのは認められない。
④ 指導室を設置せず、会議室等を借りての通級は認められない。
⑤ 巡回指導員を迎えて別室での通級は、校内職員と身分が違うので認められない。
***
法律面を学ぶことは、教材研究や子ども理解などと同じく、重要です。
新しい先生は、法律面は難しいから、教材研究の研修から、とはなりません。
特に一人教室では、法律面を押さえておかないと、教室運営に重大な問題が発生することがあります。
新人研修のあり方をもっと体系的に、総合的に組み立てる必要があります。

↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
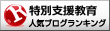
***
① 校内の特別支援学級への通級は、認められない。
② 近隣の療育センターへの通級は、施設の位置づけが不明確なら認められない。
③ 軽度難聴の子が、授業時間に近隣の聾学校へ通級するのは認められない。
④ 指導室を設置せず、会議室等を借りての通級は認められない。
⑤ 巡回指導員を迎えて別室での通級は、校内職員と身分が違うので認められない。
***
法律面を学ぶことは、教材研究や子ども理解などと同じく、重要です。
新しい先生は、法律面は難しいから、教材研究の研修から、とはなりません。
特に一人教室では、法律面を押さえておかないと、教室運営に重大な問題が発生することがあります。
新人研修のあり方をもっと体系的に、総合的に組み立てる必要があります。
↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
***
2016.01.11
この研究主題は、古くて新しい
研究主題「ことばを支える『心の育ち』を大切にした支援のあり方を考える」
研究の柱
1
その子をどのように理解していくか。
→子どもの実態把握
2
その子にとっての問題をどのようにおさえ、問題の発生と経過をどうとらえるか。
→子ども理解の仮説
3
その子にとっての必要な育ちとは何か。どのようにかかわり支援するか。
→支援の計画と実際
4
支援の経過をどのように振り返り、関係者と情報共有するか。
→支援の省察と共有
各研究の柱の意図は以下の通りです。
(1)「その子どものどこをどのように観て、理解していくのか」「その子どもを担当者はどんな姿勢で理解していくのか」ということを考えます。「ことば」「聞こえ」という側面だけでなく、多面的な視点で総合的に子どもを観て、支援の方向付けにつなげていきます。
(2)その子どもの困っていることや保護者の心配が「どのように発生したか」の筋道を考えます。実態把握で得た情報を基に、「その子どもにとっての問題」を明らかにし、その子がどのような育ちの中で現在の状態に至ったのかの要因を探り、仮説を立てながら理解を深めていきます。
(3)これまでにとらえた「その子どもにとっての問題」とその子どもの「育ち」、その中の「問題が発生してきた背景」の理解を基に、どう子どもと保護者を支えていくかを考えていきます。また、「今、その子に必要な支援は何か」を常に考えながら支援に当たります。
(4)事例を中心とした研究を進めるために、担当者が指導過程での自分の実践の考えや思いを丁寧に振り返り、省みて(=省察)いきます。個人の記録で、周りの担当者との交流で、教室研修やブロック研修で、大会発表でと、様々な機会を利用して省察・共有し、研究を進めていきたいと考えます。
***
さて、「言語障害教育」での実践を「古い」と評価し、「最新の学説」と対置させるような議論が散見されます。
「発音よりも、学習面の支援が重要なのでは?」など。
しかし、それは、「言語障害教育」の研究実践への誤解です。
上記の研究主題を読んでいただければわかるように、「言語障害教育」は、初めから、「ことば、きこえ」という側面だけでなく、その背景を徹底的に見ようとしてきました。
構音練習ばかりやっているというわけではないのです。
道言協の研究主題は、「言語障害」にとどまらず、どの子、どの関係者にも必要な、古くて新しい視点である、と思います。
今度の小樽の臨床研では、後半で、構音障害の基礎講座をお願いされました。
直前まで、パワーポイントを整理しようとしていましたが、手が動きませんでした。
何かもやもや感が。
そして、もやもや感の原因がわかりました。
基礎知識の研修もするけれど、より実践的な研修にしようと。
そしてトータルな子ども理解の力をつけられるような研修にしようと。
せっかく道言協の研究主題が設定されているのですから、これを使います。
ある事例について、教育相談事例研修です。
その子についての、「子ども理解の仮説」、「支援の計画と実際」をワークシートを使って、少人数グループで協議します。
そこに検査、相談の実技をはめ込み、OJTの要素を入れていきます。
どうでしょう?

↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
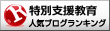
***
研究の柱
1
その子をどのように理解していくか。
→子どもの実態把握
2
その子にとっての問題をどのようにおさえ、問題の発生と経過をどうとらえるか。
→子ども理解の仮説
3
その子にとっての必要な育ちとは何か。どのようにかかわり支援するか。
→支援の計画と実際
4
支援の経過をどのように振り返り、関係者と情報共有するか。
→支援の省察と共有
各研究の柱の意図は以下の通りです。
(1)「その子どものどこをどのように観て、理解していくのか」「その子どもを担当者はどんな姿勢で理解していくのか」ということを考えます。「ことば」「聞こえ」という側面だけでなく、多面的な視点で総合的に子どもを観て、支援の方向付けにつなげていきます。
(2)その子どもの困っていることや保護者の心配が「どのように発生したか」の筋道を考えます。実態把握で得た情報を基に、「その子どもにとっての問題」を明らかにし、その子がどのような育ちの中で現在の状態に至ったのかの要因を探り、仮説を立てながら理解を深めていきます。
(3)これまでにとらえた「その子どもにとっての問題」とその子どもの「育ち」、その中の「問題が発生してきた背景」の理解を基に、どう子どもと保護者を支えていくかを考えていきます。また、「今、その子に必要な支援は何か」を常に考えながら支援に当たります。
(4)事例を中心とした研究を進めるために、担当者が指導過程での自分の実践の考えや思いを丁寧に振り返り、省みて(=省察)いきます。個人の記録で、周りの担当者との交流で、教室研修やブロック研修で、大会発表でと、様々な機会を利用して省察・共有し、研究を進めていきたいと考えます。
***
さて、「言語障害教育」での実践を「古い」と評価し、「最新の学説」と対置させるような議論が散見されます。
「発音よりも、学習面の支援が重要なのでは?」など。
しかし、それは、「言語障害教育」の研究実践への誤解です。
上記の研究主題を読んでいただければわかるように、「言語障害教育」は、初めから、「ことば、きこえ」という側面だけでなく、その背景を徹底的に見ようとしてきました。
構音練習ばかりやっているというわけではないのです。
道言協の研究主題は、「言語障害」にとどまらず、どの子、どの関係者にも必要な、古くて新しい視点である、と思います。
今度の小樽の臨床研では、後半で、構音障害の基礎講座をお願いされました。
直前まで、パワーポイントを整理しようとしていましたが、手が動きませんでした。
何かもやもや感が。
そして、もやもや感の原因がわかりました。
基礎知識の研修もするけれど、より実践的な研修にしようと。
そしてトータルな子ども理解の力をつけられるような研修にしようと。
せっかく道言協の研究主題が設定されているのですから、これを使います。
ある事例について、教育相談事例研修です。
その子についての、「子ども理解の仮説」、「支援の計画と実際」をワークシートを使って、少人数グループで協議します。
そこに検査、相談の実技をはめ込み、OJTの要素を入れていきます。
どうでしょう?
↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
***
2015.12.30
難聴が疑われる就学児。気導聴力検査で不適切なのはどれか。
1 大きい音から聞かせ、徐々に小さくする。
2 左右のうち、健側から測る。
3 機械のスイッチを押すところは見えいないようにする。
4 1000Hzから始める。
5 1000Hzは2回測る。
***
一対一では聞こえに問題がないからと言って、聴力が正常とは限りません。
集団の中で、わずかの雑音があるととても聞き取りにくくなったり、
音源が遠い(座席が後ろの方など)と聞き取りにくい。
後ろから話しかけられると、話しかけられたこと自体に後で気づくなど。
集団での様子のアセスメント、そして聴力検査が重要です。
学習障害を疑うなら、必ず聴力検査の情報を頂くか、自ら検査すること。
就学時健診での聴力検査は上記より簡易なものですが、それを行わないのは違法です。
自治体規模で実施するか否かを決めるのはおかしい。
法で定められている以上、必ずやらなければならないのです。

↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
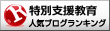
***
2 左右のうち、健側から測る。
3 機械のスイッチを押すところは見えいないようにする。
4 1000Hzから始める。
5 1000Hzは2回測る。
***
一対一では聞こえに問題がないからと言って、聴力が正常とは限りません。
集団の中で、わずかの雑音があるととても聞き取りにくくなったり、
音源が遠い(座席が後ろの方など)と聞き取りにくい。
後ろから話しかけられると、話しかけられたこと自体に後で気づくなど。
集団での様子のアセスメント、そして聴力検査が重要です。
学習障害を疑うなら、必ず聴力検査の情報を頂くか、自ら検査すること。
就学時健診での聴力検査は上記より簡易なものですが、それを行わないのは違法です。
自治体規模で実施するか否かを決めるのはおかしい。
法で定められている以上、必ずやらなければならないのです。
↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
***
2015.12.25
学校ではどもらないのに、家庭ではどもる小4男児の保護者支援でもっとも適切なのはどれか。
2015.12.23
「学習の遅れが心配」を主訴に訪れた小3男児。適切な対応はどれか。
2015.12.19
WISCの解釈の研修会も大事ですが、そもそも、マニュアル通りに実施しているのか
WISCについて、「解釈」の研修会も大事ですが、そもそも、マニュアル通りに実施しているのかということが問題。
正解が出るまで、規定以上のヒントを出し続けたり、視覚的な提示も求められている課題で、口頭だけで提示したり・・・。
何度も我流のやり方をしていると、マニュアルから外れていることもわからなくなります。
他の人に癖を指摘してもらう必要があります。
ヒントを出し続けて正解を導くようなやり方は、そもそも「標準化された検査」の意味がわかっていない。
ましてや、我流で行った検査結果を他人が解釈するとなると、二重三重のバイアスがかかることになり、きわめて危険です。
他人が解釈するなら、検査実施者に実施能力があるかを見定めなければなりません。
”OJT”
実技の中で研修する会を冬休み中に持ちます。
知識はあっても、実際はどうなのか、ということを学ぶ。
そして、知的な遅れ、言語能力全般の遅れがあるのに、読み書きの状態だけで、「ディスレキシア」と判断してしまったり、一事象だけで障害を判断してしまったり・・・。
就学相談の面接の進め方、障害のとらえ方、アセスメントの取り方など、イロハのイから。
新しい先生が多いこの地方では、難しい解釈の前に、基本中の基本から研修するニーズが高いです。

↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
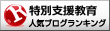
***
正解が出るまで、規定以上のヒントを出し続けたり、視覚的な提示も求められている課題で、口頭だけで提示したり・・・。
何度も我流のやり方をしていると、マニュアルから外れていることもわからなくなります。
他の人に癖を指摘してもらう必要があります。
ヒントを出し続けて正解を導くようなやり方は、そもそも「標準化された検査」の意味がわかっていない。
ましてや、我流で行った検査結果を他人が解釈するとなると、二重三重のバイアスがかかることになり、きわめて危険です。
他人が解釈するなら、検査実施者に実施能力があるかを見定めなければなりません。
”OJT”
実技の中で研修する会を冬休み中に持ちます。
知識はあっても、実際はどうなのか、ということを学ぶ。
そして、知的な遅れ、言語能力全般の遅れがあるのに、読み書きの状態だけで、「ディスレキシア」と判断してしまったり、一事象だけで障害を判断してしまったり・・・。
就学相談の面接の進め方、障害のとらえ方、アセスメントの取り方など、イロハのイから。
新しい先生が多いこの地方では、難しい解釈の前に、基本中の基本から研修するニーズが高いです。
↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
***

 管理画面
管理画面



