某公立学校ことばの教室教員。公認心理師、言語聴覚士、特別支援教育士。
『クイズで学ぶことばの教室基本の「キ」』の著者。
SINCE 2000.1.1
プロフィール
ハンドルネーム ya
某公立学校通級指導教室担当教員
言語聴覚士
特別支援教育士(S.E.N.S)
性別 男
■メールはこちら
■ツイッターはこちら
■ことばの教室ビギナーズ交流館(DVD頒布者限定パスワード)
■一日1クリックを。ランキングに反映します。
もくじ
ブログ内検索
カレンダー
最新コメント
[01/11 board]
[11/21 西村徹]
[02/23 留萌小学校ことばの教室]
[05/10 プー子]
[01/11 にくきゅう]
[11/25 なっか]
[10/26 さつき]
[10/12 赤根 修]
[08/21 赤根 修]
[05/28 miki]
[05/28 miki]
[05/13 赤根 修]
[05/06 赤根 修]
[04/15 miki]
[04/15 赤根 修]
[03/12 かわ]
[03/09 赤根 修]
[03/03 KY@札幌]
[03/01 赤根 修]
[02/28 hakarino]
[02/23 kさん]
[02/23 miki]
[02/12 suge]
[01/15 suge]
[01/15 miki]
アクセス解析
2025.02.02
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2015.05.27
ことばの教室担当教員の「本務」と「校務分掌」
この問題は古くて新しいのですが。
通級担当の本務、校務分掌の仕事との関係については、
「通級学級に関する調査研究協力者会議」(平成5年3月31日、文部省諮問機関。山口薫座長)が答申しています。
つまり、通級担当の勤務体系は特殊であるために、校務分掌などについて配慮すべきと明示しています。
この答申を受けて、文部省は通級制度を開始したという歴史を振り返る必要があります。
校務分掌の仕事のために、週1回の指導を休みにするということは、
通常学級での授業を一週間休むのと同じです。
構音が改善途中にあるのに、1回休むことで、汎化が難しい子は元に戻ってしまいます。
心理的な支援が必要なお子さんには、週1回の場を奪われることで、事態が深刻化する場合もあります。
校務分掌の仕事のために、通常学級の授業を休むことがないでしょう?
ことばの担当が補欠に入ることを求められるが、逆に通常学級の先生が、ことばの教室に補欠に入って頂けるのですか?
構音指導の進め方についての補欠指導案を書いておくので、その通りにしてください。
できないでしょ?
それぞれの部署での専門性、事情を配慮しない学校は、組織体とは言えません。
指導を休みにすることは、通級している子の「学習権」を侵害しており、教育の機会均等、合理的配慮違反です。
かつてことばの担当のための大学の専攻課程がありましたが、今は北海道にはなくなりました。
だから現職についてからの研修が必須です。
そのための時間も必要です。
と、たとえ話で、私はお話ししています。
ことばの担当は、どうしても、職員の中ではマイナーです。
数が少ないからです。
相談相手も校内に居ません。
だから、横のつながり、組織が大切です。
親の会が大切です。
通っている親、当事者の声を校長、行政に届ける必要があります。
ことばの教室は親の会の運動によって設置されてきました。
だから、親の会を軽視してはいけないのです。

↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
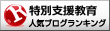
***
通級担当の本務、校務分掌の仕事との関係については、
「通級学級に関する調査研究協力者会議」(平成5年3月31日、文部省諮問機関。山口薫座長)が答申しています。
つまり、通級担当の勤務体系は特殊であるために、校務分掌などについて配慮すべきと明示しています。
この答申を受けて、文部省は通級制度を開始したという歴史を振り返る必要があります。
校務分掌の仕事のために、週1回の指導を休みにするということは、
通常学級での授業を一週間休むのと同じです。
構音が改善途中にあるのに、1回休むことで、汎化が難しい子は元に戻ってしまいます。
心理的な支援が必要なお子さんには、週1回の場を奪われることで、事態が深刻化する場合もあります。
校務分掌の仕事のために、通常学級の授業を休むことがないでしょう?
ことばの担当が補欠に入ることを求められるが、逆に通常学級の先生が、ことばの教室に補欠に入って頂けるのですか?
構音指導の進め方についての補欠指導案を書いておくので、その通りにしてください。
できないでしょ?
それぞれの部署での専門性、事情を配慮しない学校は、組織体とは言えません。
指導を休みにすることは、通級している子の「学習権」を侵害しており、教育の機会均等、合理的配慮違反です。
かつてことばの担当のための大学の専攻課程がありましたが、今は北海道にはなくなりました。
だから現職についてからの研修が必須です。
そのための時間も必要です。
と、たとえ話で、私はお話ししています。
ことばの担当は、どうしても、職員の中ではマイナーです。
数が少ないからです。
相談相手も校内に居ません。
だから、横のつながり、組織が大切です。
親の会が大切です。
通っている親、当事者の声を校長、行政に届ける必要があります。
ことばの教室は親の会の運動によって設置されてきました。
だから、親の会を軽視してはいけないのです。
↑ 特別支援教育ブログランキング。1クリックを
***
PR
Comment
ことばの教室に通っている子どもたちにとっては、ごくごくあたりまえのことなんですが。部活動より、学校の授業より「ことばの訓練」が優先の子どもたちがたくさんたくさんいました。ことばの教室は、「言語治療学級」での1時間の訓練で、子どもの人生が左右されるかもしれない、親の会のみなさんは、それぐらいの気迫があったと思います。ことばは目に見えないから、しょうがいがあっても、わかりにくく、本人も困り感をうまく表現できません。日常生活が遅れるまで、長い時間がかかる生徒もまだまだいます。
発達しょうがいの理解が広がっている今だからこそ、たくさんのおとなに理解してほしいです。
ya先生、お忙しい時期と思いますが、どうか、無理をなさらないでね。応援しています。
発達しょうがいの理解が広がっている今だからこそ、たくさんのおとなに理解してほしいです。
ya先生、お忙しい時期と思いますが、どうか、無理をなさらないでね。応援しています。
私はこの道19年目になりましたが、以前に比べると、ことばの教室担当が、校務分掌の仕事や補欠授業などでとても忙しくなっているように感じます。かつて親の会が「1時間の指導のためには一時間の教材研究を」と言っていた時代と比べると、教材研究の一つも満足にできない状態です。
専門職としての地位保全のための制度設計がどうしても必要と思っています。
専門職としての地位保全のための制度設計がどうしても必要と思っています。
わ、すごい誤字がありました。重ね重ね申し訳ない(<m(__)m>

 管理画面
管理画面




